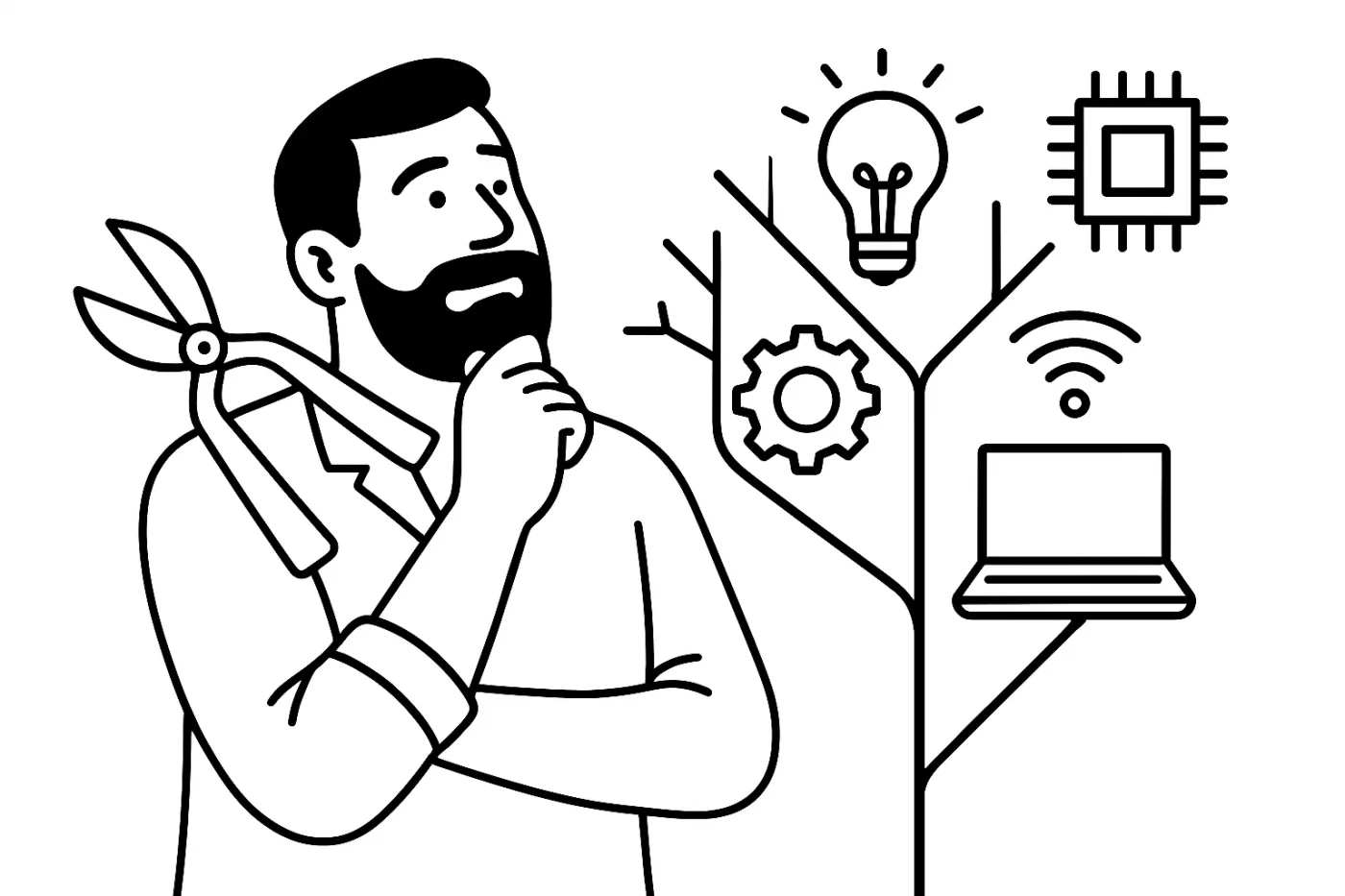なぜ今、経営に「剪定」の発想が必要なのか
現代の経営者が直面する最大の課題は何か。それは選択肢の多さである。
デジタル化、グローバル化、多様化が進む中で、企業は日々無数の判断を迫られる。新しい技術、新しい市場、新しい人材、新しいパートナーシップ。すべてが「可能性」として目の前に現れ、経営者の判断力を試し続けている。
この状況で多くの企業が陥るのが「選択麻痺」だ。あれもこれもと手を出した結果、リソースが分散し、本来の強みが埋もれてしまう。一方で、コスト削減や人員整理に走りすぎて、成長の芽まで摘んでしまう企業も少なくない。
そこで注目したいのが「剪定能(せんていのう)」を活かした新しいマネジメント思考である。
剪定能とは何か
剪定能とは、思考・情報・デザインにおける「余分を削ぎ落とす力」であり、同時に「脳内の雑多な思考を整理する力」でもある。
木の枝を剪定するように、不要なものを切り落とし、必要なものを残し、全体を健やかに、美しく整える。この二重の意味を持つ「能(能力/脳)」により、剪定能は単なる整理術にとどまらず、生き方や創造性を支える根本的な能力として位置づけられる。
剪定能の基本概念
1. 削除≠剪定の原則
- 削除:不要なものを取り除いて終了
- 剪定:不要なものを取り除き、残したものに集中投資してReGrow(再成長)させる
2. ReGrow能力としての本質
- 剪定の目的は「削ること」ではなく「育てること」
- 浮いたリソースを核心業務に集中投資
- 組織や事業の再生・再成長を促進
3. 全体最適の視点
- 部分的な効率化ではなく、システム全体の健全性を重視
- 短期的な削減ではなく、長期的な成長戦略
剪定マネジメントの実践
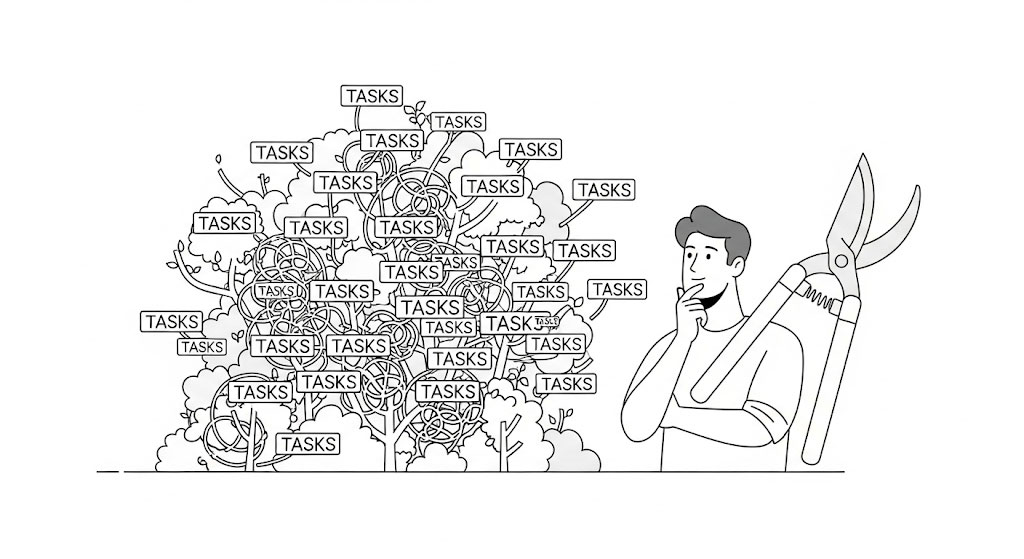
ケーススタディ:赤字部門の「剪定」
従来のアプローチなら、赤字部門はリストラや事業撤退の対象となる。しかし剪定マネジメントでは、まず部門内の「剪定箇所」を特定する。
剪定プロセス:
- 無駄な業務プロセスの特定(剪定箇所の診断)
- 不要な作業・会議・システムの削減(実際の剪定)
- 浮いたリソースの核心業務への集中投資(肥料やり)
ある企業では、営業部門の業務を剪定した結果、30%の工数削減を実現。その浮いたリソースを顧客開拓と既存顧客フォローに集中投資することで、売上を25%向上させることができた。
組織運営における剪定能
組織においても剪定能は威力を発揮する。会議の剪定、報告業務の剪定、意思決定プロセスの剪定。それぞれで浮いた時間を、本来集中すべきコア業務に振り向けることで、組織全体のパフォーマンスが向上する。
他分野への応用可能性
剪定マネジメントの思考は、経営以外の分野でも威力を発揮する。
剪定能の応用分野
1. デザイン分野
- 色や形を剪定し、必要最小限で最大の美を引き出す
- 機能の剪定により、ユーザビリティを向上
- 情報の剪定により、メッセージを明確化
2. ライフスタイル分野
- モノや情報を剪定し、軽やかに生きる
- 人間関係の剪定により、深い絆を育む
- 時間の使い方を剪定し、本当に大切なことに集中
3. スポーツ分野
- 無駄な動きを剪定し、効率的なフォームを追求
- 練習メニューを剪定し、重点技術の習得に集中
- 戦術を剪定し、チームの特長を最大化
剪定能を育てる実践的手法
剪定能は生まれ持った才能ではない。適切な訓練により、誰でも身につけることができる能力である。
剪定能育成の3ステップ
1. 現状の可視化
- 業務、思考、情報の流れを客観的に把握
- 何にどれだけのリソースを使っているかを明確化
2. 剪定箇所の特定
- 本当に必要な要素と不要な要素の仕分け
- 「削除してよいもの」と「残すべきもの」の判別
3. 集中投資の実行
- 浮いたリソースを戦略的に再配分
- 成果を測定し、継続的に改善
弊社における剪定マネジメントの実績
これらの概念は、弊社が長年にわたって実践してきたマネジメント手法を言語化したものである。
1995年代のプロバイダー事業から始まり、ウエブサイト制作、システム開発へと事業を転換してきた過程で、常に「何を残し、何を育てるか」という剪定の思想が根底にあった。
事業の選択と集中、組織の最適化、技術の取捨選択。すべてにおいて剪定能を活用することで、変化の激しいIT業界で30年近くにわたって事業を継続してきた実績がある。
剪定マネジメントが拓く未来
AIやデジタル技術が発達した現代こそ、人間の剪定能がより重要になっている。
技術ができることは技術に任せ、人間は「何を選び、何を育てるか」という判断に集中する。これこそが、これからの経営者に求められる核心的な能力である。
剪定能を身につけた経営者は、複雑な現代において迷うことなく、本質を見抜き、組織を健やかに成長させることができる。
それは単なるコストカットでも、闇雲な拡大でもない。まさに「育てるための剪定」なのである。

「剪定能」の概念は、有限会社ビーアイティー(BIT)が提唱する「概念創造型マーケティング」の実践手法のひとつです。